こんにちは、モブ農です。
有機JASというと、「こだわりの農家」「意識の高い農業」といったイメージを持たれることが多いですよね。
でも私にとっての有機JASは、そうした“思想”ではなく、もっと実務的なものです。
それはつまり——
販売の有利性・栽培の基準・他の生産者との共通言語
この3つのためにあると考えています。
販売の有利性:ルールがあるから売りやすい
有機JASのマークは、単なる飾りではなく「取引上の信頼の証」だと思います。
とくに加工業者やスーパーなど、仕入れ先の多くがJASマークを取引条件にしています。
私自身も、JAS認証を取ってから「書類ひとつで話が進む」場面が増えました。
「肥料は何を?」「農薬履歴を見せて」など、細かい確認をされる前に、
JASの基準そのものが“信頼の下地”になってくれるんです。
栽培の基準:判断の“軸”ができる
有機JASの栽培基準は、日々の判断に迷ったときの拠り所になります。
「この資材は使っていいのか?」「除草はこれで問題ないのか?」
そんなとき、JAS基準を“軸”として持っていれば、迷いを減らすことができます。
もちろん、JASのルールが万能というわけではありません。
「もっと効率的にできるのに」と感じることもあります。
それでも、他人に説明できる共通ルールを持つことには大きな意味があると思います。
他の生産者との共通言語
有機JASのもうひとつの価値は、他の生産者との会話がスムーズになることです。
「どの認証団体?」「施肥設計は?」といった話をすれば、
お互いの考え方や方向性がすぐに伝わる。
“有機”といっても考え方は十人十色ですが、
JASという最低限の基準があることで、情報交換や共同出荷のベースが作れる。
これは、地域で農業を続けていくうえでとても大きいと感じます。
「思想」ではなく「実務」の認証
私にとって有機JASは、「こだわり」ではなく「仕組み」です。
栽培・販売・連携、それぞれの現場をスムーズに動かすための共通ルール。
ルールのある世界で栽培し、販売し、仲間と共有する。
その積み重ねが、結果として地域の農業を安定させるのではないかと思っています。
まとめ
- 有機JASは「販売の信頼」「栽培の基準」「生産者の共通言語」。
- 思想ではなく、現場を動かす“実務の仕組み”。
- ルールがあるからこそ、迷わず、つながりやすくなる。
🌱 畑にいるよ。
ルールに縛られるより、ルールを活かしていく農業をしたいと思っています。
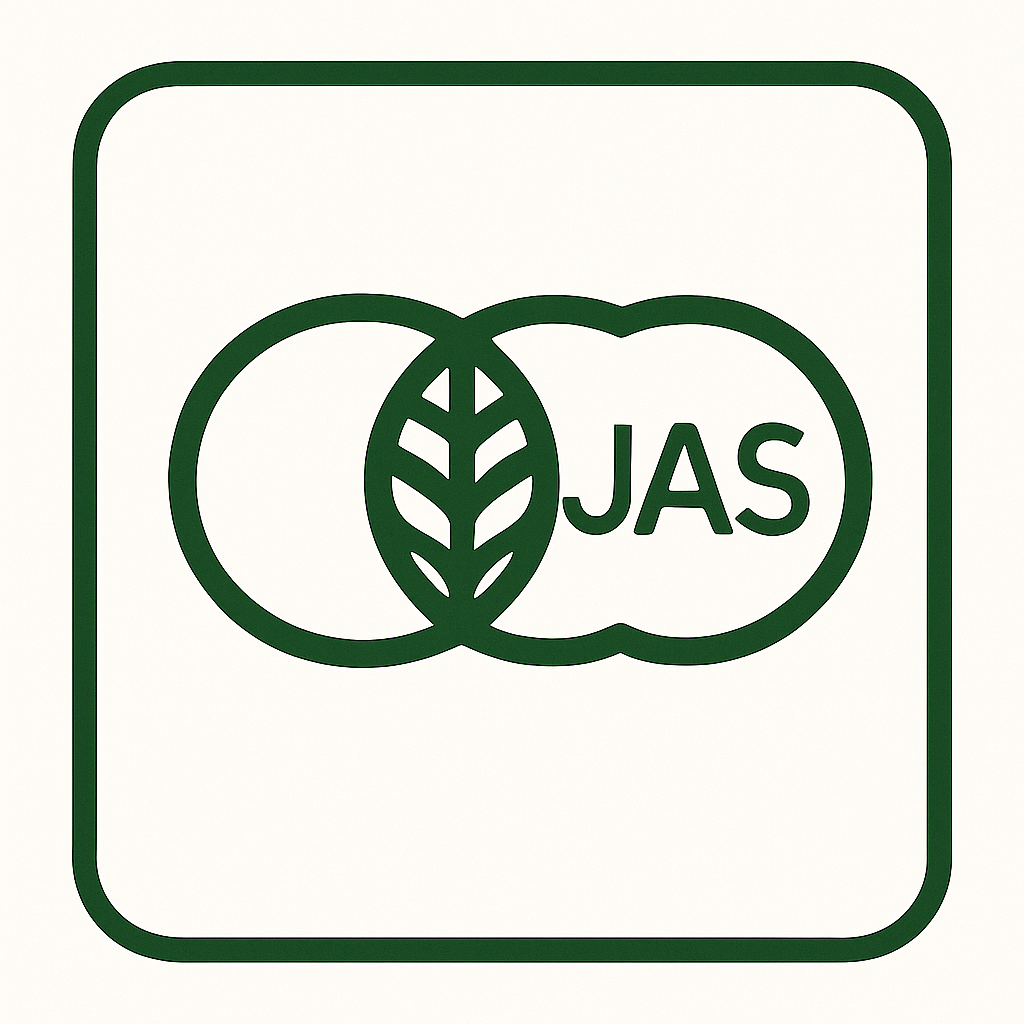


コメント