こんにちは、モブ農です。
私の圃場では、ほとんどの畑でカリウム(K)が高めに出ます。
分析では「300mg/100g」という数値もあり、最初はそれを見て焦りました。
「カリウム過多=悪い」と思い込み、とにかく減らそうと必死だったんです。
でも、いろいろな圃場を見て、実際に作物の反応を観察していくうちに、
“カリウムという元素は、数字だけで判断できない”と感じるようになりました。
火山灰土壌は「カリを握る土」だと思う
私の圃場は火山灰土壌です。
CEC(陽イオン交換容量)が25〜35と高く、カリウムを強く吸着して離しにくい性質があります。
つまり、「カリが多い」というより、「土がカリを溜め込みやすい構造」になっているように思います。
そのため、これ以上カリを入れなくても、土の中にはしっかりストックがある。
ただし、CaやMgを押しのけて吸着してしまうため、バランスが崩れてCa・Mgが効きにくい現象が起きやすいと感じています。
「5:2:1」に振り回された時期
一時期、「Ca:Mg:K=5:2:1」という理想比を信じて、分析値をそのままmg/100gで当てはめていました。
すると「Kは50が理想だ」と思い込み、どの圃場もKを下げようとしていたんです。
ところが、実際にはこの5:2:1という比率は**塩基飽和比(cmol比)**の話であり、
mg値とはまったく意味が違うことに後から気づきました。
CECの高い火山灰土壌では、Kが100前後あってようやく塩基飽和で5%前後。
つまり、「K100」がちょうど理想だったわけです。
「K50にしよう」としていた頃の私は、むしろ土を貧しくしていたかもしれないと今は思います。
耕作放棄地でもカリウムが高い理由
新しく借りた放棄地も、長年無施肥のはずなのにKが100前後で出ることがあります。
最初は不思議でしたが、よく考えるとこれは自然なことなんですよね。
雑草が生え、枯れて、また生える──
この繰り返しの中でKは常にリサイクルされています。
カリウムは水溶性で、分解を待たずにすぐ再利用される元素。
つまり、「自然のK循環」がしっかり働いているということなんだと思います。
火山灰土壌はKを握りやすいので、外から何も入れなくてもKが減りにくい。
むしろ、自然状態で100前後あるのが“普通”ではないかと感じています。
対照的に、水田はKが抜けていく
一方、長年水稲を作っている田んぼでは、Kが驚くほど低く出ることがあります。
湛水による溶脱、還元状態での脱着、そしてワラの持ち出しによる搬出…。
田んぼは「Kを溜める場所」ではなく、「Kを持っていかれる場所」なんですよね。
同じ地域でも、畑と水田でKの動きがまったく違うのが面白いところです。
私の今の考え方
- カリウムは“入れる”より“動かす”ものだと思っています。
緑肥や有機酸の力で、固定されているKをゆっくり動かす。 - Kを減らすのではなく、Ca・Mgとの均衡で考える。
K100前後、Mg60前後、Ca300くらい。
このバランスがしっくりくるように思います。 - K過多よりも“Kが動かない”ことの方が問題。
緑肥と苦土で、Kを動かす環境を整えていくことが大事ではないかと考えています。
まとめ
カリウムの数字に振り回されず、「なぜその数字になっているのか」を見極めることが大切。
Kが高いのは、悪いことではなく“握りやすい土の個性”かもしれません。
重要なのは、Ca・Mgとのバランスと、カリがちゃんと“動く環境”をつくること。
📘 モブ農の結論:
「カリウムは悪者じゃない。
土がどう抱えて、どう動かしているかを見れば、
その土地の性格が少しずつ見えてくるように思います。」
🌱 畑にいるよ。
今日も、数字より“土の声”を聞く日になりそうです。
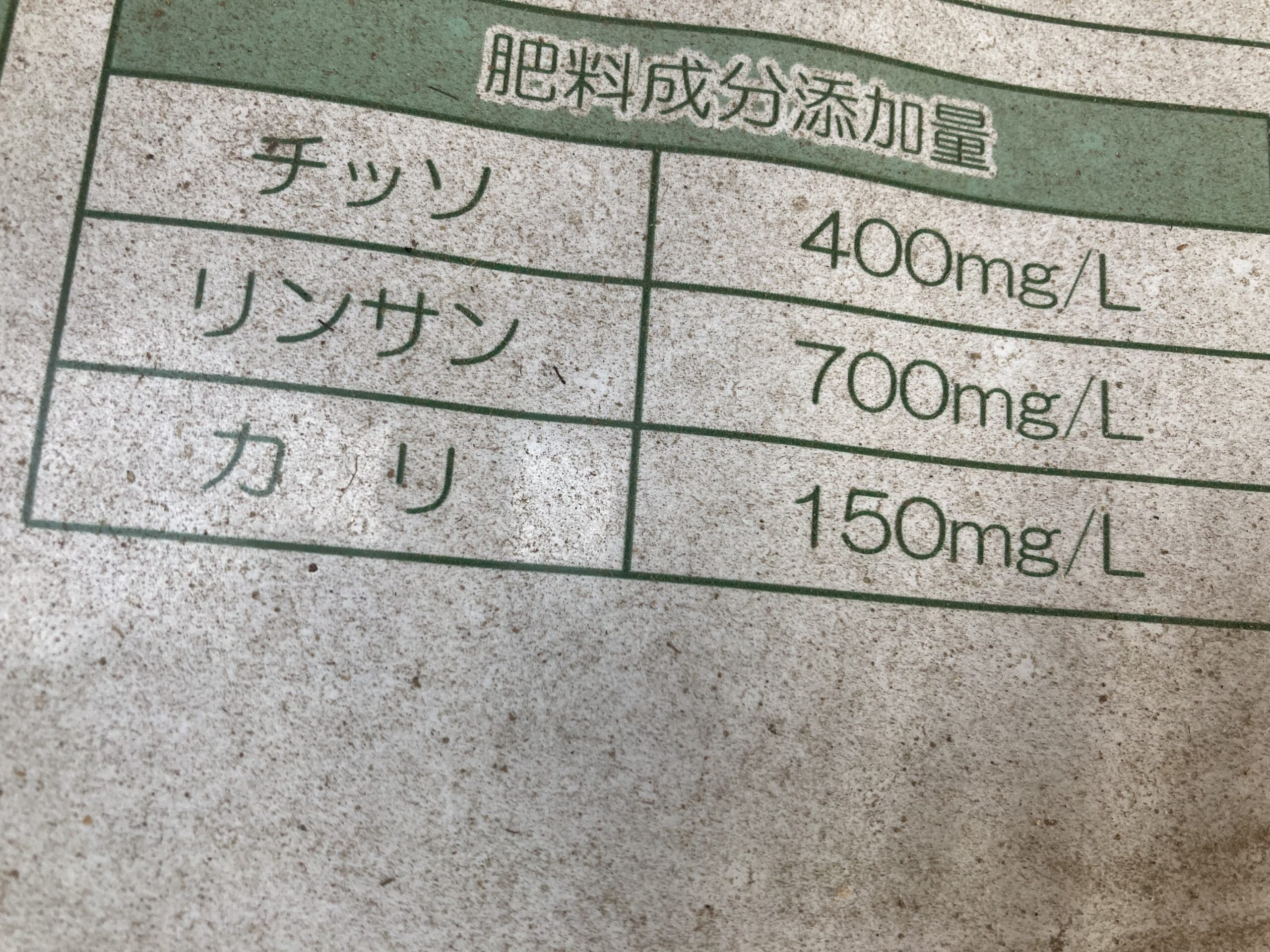


コメント