こんにちは、モブ農です。
最近、「日本の米は高い」「生産性が低い」「輸入でいい」という話をよく聞きます。
でも実際に現場で農業をしている立場から見ると、その多くは“条件が違う比較”なんです。
私は野菜農家で、田んぼは10アールほど。米づくりが専門ではありませんが、農家として・一市民として、現場を見ていて感じることを書いてみます。
本当に日本の米は生産性が低いのか?
数字で見てみると、意外な事実があります。
- コシヒカリ系:500〜550kg / 10a
- 多収穫品種:700〜850kg / 10a
- アメリカ米(長粒種):850〜900kg / 10a
つまり、日本の米は世界でも高い収量を安定して出している。
しかも、狭い圃場・複雑な地形・高齢化という条件の中で、です。
「非効率」と言われがちですが、それは“条件を無視した効率論”。
日本の農家の技術は、むしろ驚くほど高いレベルにあります。
「日本の米は農薬まみれ」―― それは誤解です
実際の現場ではこうです。
- 除草剤:使う(草取りの時間を確保するため)
- 殺虫剤・殺菌剤:年によってはほぼゼロ
病害虫が出ない年なら、除草剤だけで収穫までいく田もあります。
逆にアメリカでは、大規模・直播中心のため強力な除草剤を空から散布するケースも。
さらに、日本は世界で最も農薬規制が厳しい国のひとつ。
実際のところ、「日本の米は危ない」どころか、世界で最も安全な米です。
「補助金まみれ」でもない日本農業
よく「日本の農家は補助金で守られている」と言われますが、数字は逆です。
- 🇯🇵 日本:農家所得に占める補助金 約10〜15%
- 🇺🇸 アメリカ:20〜30%
- 🇪🇺 EU:30〜40%
アメリカでは価格下落時に自動で補填(PLC制度)、EUでは面積ごとの直接支払い。
一方の日本は、転作や景観保全といった“間接的支援”ばかり。
つまり、日本の農家は市場リスクを自分で背負っているのです。
実は「国産のほうが地球にやさしい」
輸送距離の差を見てみましょう。
- アメリカ → 日本(約8,000km):CO₂ 約120kg / トン
- 日本国内(約500km):CO₂ 約50kg / トン
つまり、輸入米のCO₂排出量は国産の2倍以上。
「安い輸入米でいい」は、環境面では正しくありません。
“地産地消”は安全のためだけでなく、地球のための選択でもあるんです。
大規模化の影にあるリスク
効率化=良いこと、と思われがちですが、実際はそれだけではありません。
- 農家の数が減る → 水路の管理が難しくなる
- 小さな田が切り捨てられ → 放棄地が増える
- 放棄地が増える → 獣害・洪水・渇水のリスク増大
農業は“1人の生産性”ではなく、地域全体の維持と支え合いが前提です。
効率化が地域を弱くすることもある――。それが現場の実感です。
中山間の田んぼは「非効率」でも価値がある
上流の田んぼには、こんな役割があります。
- 雨水を貯めてゆっくり流す「天然のダム」
- 地下水を育て、下流の水位を安定させる
- 土砂流出を防ぎ、災害リスクを減らす
中山間の田は“見えないインフラ”。
経済性だけでは測れない価値を持っています。
「全部守る」ではなく「生きている田を守る」
山奥で水を引くだけで精一杯の田や、耕作が不可能な田は、
牧草地・ビオトープ・そば・大豆など、別の形で活かす方法もあります。
大切なのは、
「全部を守る」ではなく「生きている田を守る」
という考え方です。
食料=国防
食料は、安全保障の根幹です。
もし輸入が止まったら、日本で食べられるのは国産の米だけ。
米は、
- 国内で栽培できる
- 種や肥料も国産化可能 だとおもう (私は可能だと思います)
- 長期保存できる
つまり、日本が唯一自力で守れる主食なんです。
中山間の田、水路、地域の農家。
それらはすべて、武器を持たない「国防インフラ」。
「農地を守ることは、国を守ること」
この考え方は、アメリカやヨーロッパでは常識です。
日本だけが、米を“安く買える商品”として見てしまっている。
でも、何か起きたとき、
あなたの町で食べ物を作れるのは、地元の農家です。
モブ農的結論
米は、食料であり、経済であり、そして国防です。
田んぼがあり、人が手をかけている。
それが続いている限り、日本は強い。
🌾 畑にいるよ。今日も水の音が心を落ち着かせてくれます。

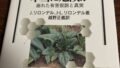

コメント